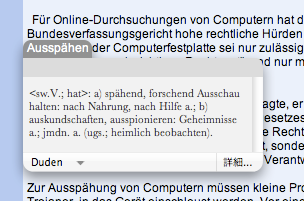寡聞にして知らなかったのだけれど、少し前、「ナンバ歩き」というのが一部で話題になっていたらしい。右足が前に出る時は左腕が前に出るような今日当たり前の歩き/走り方は、近代になって西洋から導入され定着したものであって、「昔の日本人」は、右手と右足が同時に出るような(そもそもあまり腕を振らない)歩き方・体の使い方をしていたというのだ。
甲野善紀がこの歩き方を実演してみせている動画が見られる。
この「ナンバ」の身ごなし、動きには合理性がある、
「ナンバ歩き」は「健康によい」などと主張されている。山歩きをするのに、もっぱら「ナンバ歩き」を心がけているという人もいるらしい。一方で、ほんとうに「昔の日本人」がすべてそうだったのか、現在のような歩き方・走り方はまったくしなかったのかという点については、当時の映像が残されているわけでもなく、決定的な証拠はなさそうで、不確かな言説の流布に対する批判の声も多くあがっていたようだ。ふつうにそんな歩き方するわけねーじゃねーか、という単純な否定もあちらこちらで見られる。
歴史的な事実の詳細はともかく、これがそんなに特異な動作かというと、そうでもないように思われる。日本舞踊や「古武術」では普通に行われてきている動作ではあるらしい。そう思ってみるとしかし、そもそも今現在でも、周囲にはこの「ナンバ」的なセンスの身ごなしが、実はありふれて見られることに気づく。それが見られるのは、「歩く」ことそのものとは別の場面だ。
ぼくが考えているのはクラシックの演奏の場面、アマチュア・オーケストラの練習などの場面。「ナンバ」はそれ自体の合理性はあるのかもしれないけれど、クラシックを演奏するのにこれが決定的に邪魔になっていることに気づく。どうにも音楽が形にならない人の動きというのは、多くの場合、明らかにこの「ナンバ」系なのだ。
ナンバ的な身体動作はわれわれの周囲に、むしろ歩く動作以外のところで、現にありふれているということと、クラシック音楽をやるときは、ナンバは困るということ。ここで指摘したいのはその二点だ。まさにその困る場面でこそありふれた現象として見られることに気づかれる。
おそらく、歩く動作に限っては、今日ほとんどの人が右足左腕が同時に出るクロス動作を「自然な」ものとして身につけている。ところがそれ以外の部分で、ナンバ的なセンスの動きは、しっかり生きているのだ。そのことは、それ自体悪いことであるとは思えないが、クラシックをやるときには障害になる。
それで思い出したのが、一年ほど前、ギタリストの村治佳織が、染五郎との対談で、こんなことを言っていたということだ。
村治:[...] 私は二十歳のころ日本舞踊を半年やりました。面食らったのは拍子の取り方が上から下に落ちるような感じだったこと。クラシックは下から突き上げる拍子の取り方をするのです。その感覚がうまくつかめませんでした。
染五郎:日本舞踊の動きのきっかけは歌で取ったり三味線、鼓で取ったりする。ここは唄、ここは掛け声、ここは三味線と。だからリズムで覚えようとすると絶対無理。
[日本経済新聞 2007.1.1 元旦第三部2面 新春対談「今に生きる東西の古典 伝統と新風で受け継ぐ」村治佳織、市川染五郎]
染五郎の、日本舞踊は「リズムで覚えようとすると絶対無理」という指摘は、また別に検討する必要があるかもしれないが、とりあえず村治の発言のほうに注目すると、この「上から下に落ちるような感じ」の拍子の取り方とは、「ナンバ」的な動きに他なるまい。村治が言うように、これはクラシックにはまったく馴染まない。これに対するクラシックの拍節感、村治の言う「下から突き上げる拍子の取り方」とは、アウフタクトで上向きのモーメントがあった上で第一拍に入るような動きを基本とする拍子のことだ。(音楽で普通に使われる「アウフタクト」はドイツ語。「アウフ」とは、上への動きを意味する接頭辞だ。英語のアップビートと同じことだと言ってしまった方がはやいか。)ナンバにはアウフタクトがない。
かなり前のことだが、大阪の某国立大学のオーケストラで、ブラームスの「ハイドンの主題による変奏曲」を聴いた。なんだか酒盛りで一升瓶抱えて手拍子打っているような、ひどい演奏だった。音楽が前に進んでいく感じが全くない。ぼくはそれを「花見宴会系1拍子」と呼んでいたのだが、考えてみるとこれもナンバである。要するにアウフタクト(この場合2拍子の2拍目)が死んでいて、そのまま音楽が下に落ちていき、そのつど改めて第1拍が打たれるような形になっているのは、すり足のナンバの歩みなのだ。
アマオケの中などで、うなずくように上半身を動かして拍子をとっている人がたまにいる。あれが音楽を壊し死んだ音楽を生み出すことには以前から気づいていた(だからかつて所属していたオケで、この動作を「禁止」したことがある)が、あれもナンバ系である。
練習にメトロノームを使う人は、この点でも十分に気をつけなければならない。言ってみればメトロノームはアウフタクトを知らない。拍頭を打つだけのメトロノームは、ナンバに親和性が高く、下手をするとこのナンバ的な傾向を助長するおそれがある。(そのことをしっかり把握していさえすれば、テンポの不本意な揺れをコントロールしたりするのに、メトロノームはやはり有益でありうる。)
実を言うと、クラシックの演奏の問題とナンバのことを結びつけうることを知ったのは、
深山尚久『目からウロコのポイントチェック Let’s ヴァイオリンレッスン』
(レッスンの友社、2007年)の記述からだった。そこでは深山は、ダウンボウのさいに体全体が一緒に下がっていってしまうという症例について、ナンバに結びつけて語っている。それを読んで、遅ればせながら初めてナンバのことを少し調べてみたわけだ。深山はそのようには論じていないが、これは上述のようにむしろ拍子の感覚のほうに直接的に相関した問題であると思う。
誤解のないようもう一度確認しておくが、ナンバそれ自体が悪いのではない。ナンバには特定の状況、条件ではそれ固有の合理性や有用性があるという可能性を否定するつもりはない。ただクラシックをやるには決定的に具合が悪いと言っているだけだ。場面場合によって、両方とも使い分けられるようにしておけばいいのではないか。
今ここでとくに関心を向けたいのは、ナンバという概念が、むしろわれわれのクラシックの演奏の問題点、悪い点を洗い出す上で、きわめて発見的 (heuristic) な、有益な道具となりうるということにある。演奏がどうにも不細工になってしまうがその治療法が分からない、どこがいけないのか分からない、というときに、問題を切り出す一つの鍵になりうるはずだ。